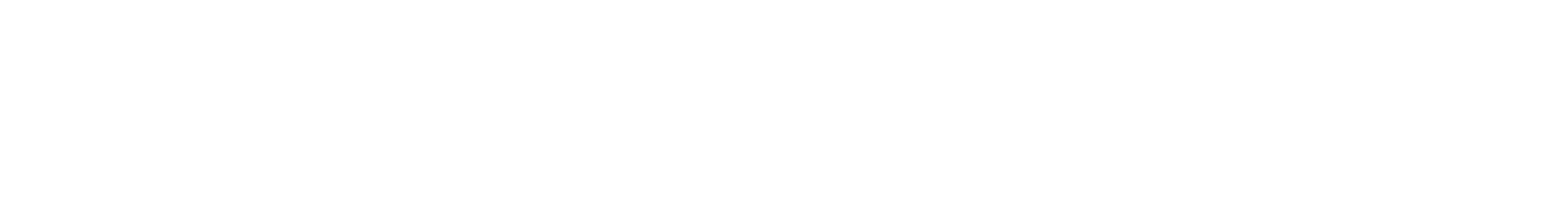「未来をひらく対話ミーティング」〜会議を超えた、組織を変える対話の力〜
「あなたの職場でのストレスはなんですか?」
2024年夏、長野市を中心に100名の女性に実施したアンケートの結果、すべての世代で最も多かったのが「人間関係」でした。
この結果は特別なものではなく、厚生労働省の調査でも、人との関係が業務量や責任感と並ぶストレス要因であることが示されています。
(BiotopeフリーペーパーVol.10特集「職場のコミュニケーションをあきらめない」より)
「上司の物言いがきつくて、つい心が閉じてしまう」
「後輩に声をかけても反応が薄く、何を考えているのかわからない」
「話し合っているはずなのに、本音は誰も口にしない」
そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?
「最近の若い子は…」は昔から言われていた
世代間ギャップは、最も身近な価値観の対立ともいえます。
実は、古代ギリシャの喜劇作家アリストファネスの作品には、若者が年長者をからかう場面が登場し、ローマ時代の哲学者セネカも「若者は年長者の忠告に耳を貸さない」と嘆いていました。
日本でも、『徒然草』をはじめ、多くの古典文学や川柳、狂言に「最近の若い者は…」「年寄りはわかってくれない」といった言葉が残っています。
つまり、私たちが今感じている「価値観の違いによるすれ違い」は、何千年も前から繰り返されてきたことなのです。
すれ違いの正体は「当たり前の違い」
年齢や育った環境、仕事観、言葉の使い方——。
「自分にとっての普通」は、相手にとっての普通とは限りません。
しかし、私たちは自分が知っている世界を基準にしてしまい、「これが常識」と思い込みがちです。この「当たり前の違い」が摩擦を生み、そのまま放置すれば、小さな違和感が積み重なり、やがて職場全体の雰囲気が悪くなってしまいます。
では、この「すれ違いの連鎖」を断ち切るにはどうしたらいいのでしょうか?
鍵は「対話」にある
ただ話すだけではなく、「相手の前提に立って理解しようとすること」。
意見を伝えるだけでなく、「なぜその考えを持っているのか」に耳を傾けること。
こうした姿勢があってこそ、対話は単なる会話を超え、人と人をつなぐ橋になります。
しかし、私たちは「対話の力」を学ぶ機会がほとんどありませんでした。
学校では「話す力」や「発表のしかた」は求められましたが、それが本当に伝わる技術として身についているとは限りません。
ましてや、「聴く力」「意見の異なる相手との対話の方法」「違和感を言葉にする技術」
を体系的に学ぶ機会はほぼありませんでした。
社会に出ても、報告・連絡・相談といった機能的なやりとりはあっても、「本音を安心して伝え合える関係づくり」までは、なかなか育てにくいのが現実です。
「聴く文化」を育てた会社の話
そんな中、ある企業が「対話の文化づくり」に本気で取り組みました。
この会社ではかつて、「若手が育たない」「ベテラン社員との衝突が絶えない」という問題がありました。そこで導入したのが、「対話ミーティング」。
定期的に部門を超えた少人数で集まり、安心して話せる場を設けたのです。
ここでは「相手の発言を否定しない」「自分の感情を主語にして話す(例:「私はこう感じた」)」
などのルールを守ることで、心理的安全性を確保しました。
最初はぎこちなかったものの、回数を重ねるうちに「普段は聞けなかった同僚の考えに触れられた」「上司の想いを初めて知った」といった声が増え、若手が主体的に動き、ベテラン社員も若手に仕事を任せる機会が増えていきました。
「なんでも言って」と言って、実は言わせていない?
この取り組みが示しているのは、
「対話の力は、特別なスキルがある人だけのものではなく、誰でも育てられる」ということ。そして何より大切なのは、「上の立場にいる人ほど、安心して話せる空気を整える役割がある」ということです。「なんでも言ってほしい」と言いながら、いざ本音を聞くと怒ったり評価したりしてしまう——。そうなると、人は、もう、口をつぐんでしまいます。「あなたはそう感じたんだね」と、一度しっかり受け止めること。その姿勢が、対話の文化の土台になるのです。
違いを受け入れ、対話のある職場へ
人間関係のストレスは、この先も完全になくなることはないかもしれません。
でも、対話を通して、そのストレスを乗り越える方法を選ぶことはできます。
違いを怖れず、わからなさを抱えて、じっくり耳を傾けること。
長野の風土のように、やさしくしなやかに。
私たちの職場にも、そんな「対話の文化」を育てていけたら素敵だと思いませんか?
BiotopeFounder
岡田 江里子
[活発性 / 着想 / 共感性]
埼玉県春日部市生まれ。国内・海外レディスブランドのファッションビジネス分野において、VMD*・セールスプロモーション・新規ブランドの立ち上げなど20年以上の経験を持つ。2017年秋、長野市へ移住。同時に市内の総合広告会社に入社し企画職に従事。自治体関連事業(移住促進・関係人口・ワーケーション)のPRを担当。担当事業に関わる中で、ソーシャルキャピタルの重要性に着目しBiotopeの構想を立案。
2020年秋:Biotope発足
【専門分野資格等】
▶︎女性向けサービス・プロダクトのマーケティング/ワーケーション/新規事業立案/ライフキャリアプラン/人材育成・開発
▶︎国家資格キャリアコンサルタント
*VMD:Visual Merchandising (ビジュアル・マーチャンダイジング)の略。「マーチャンダイジング=商品化計画」を「ビジュアル=視覚化(目に見えるように)」する。つまりVMDは「ブランドのコンセプトや企画の意思」をビジュアル化し、顧客とのコミュニケーション能力を高める手法のことをいう。